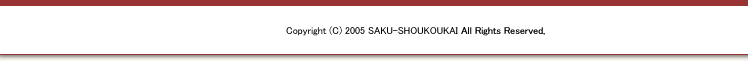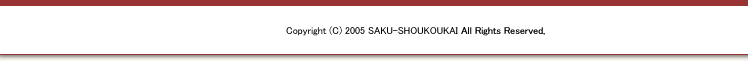大正から昭和初期まで、佐久鯉は「第一次黄金時代」を迎える。大正九年、野沢町産業組合(農協の前身)の設立と同時 に、初めての東京出荷に踏みきった。当時、東京へは貨物列車で3日間かかったが、輸送中の酸素補給、水槽の水温調整な ど技術的な不足から悪戦苦闘が続く。 個人で東京進出を試みた斉藤彦六(岸野)は、江戸川にトラック3台分の鯉を収容できる池を設けた。当時、この川には 山椒魚も住んでいたという。斉藤は、佐久から小諸まで天びん棒で鯉を運び、小諸から上野までは貨車輸送。ズックを張っ た木組み水槽を足踏みふいごで休むことなく踏み続けた。夏場は2割落ち、冬場は皆無という活魚輸送に画期的な先鞭をつ けた。
|
| ●貨物輸送 昭和3年には、貨物にキャンバス製の水槽を積んだ輸送が始められ、人力で空気を送るなど手数を要したが、鯉桶よりも多くの鯉を運べる様になった。 |
|
|
| ●活魚輸送 昭和7年ごろから、酸素ボンベと分散器によるトラック輸送が始められる。 |
|
大正十二年の関東大震災後、競って東京への販路開拓が始まったが、「野沢の鯉」「桜井の鯉」「中込の鯉」など、その名称もまちまちだった。 大正十三年、野沢町で全国初の「養鯉品評会」が開かれ、佐久の鯉も全国的なものになりつつあったことから、名称統一を望む声が一気に高まった。当初は「佐久養鯉」という名称で統一したが、何となくスッキリしなかったことから更に検討された。 ブランド商品として「佐久鯉(さくごい)」の名が正式に決まったのは昭和5年。活魚輸送の専用貨車の登場とあいまって、四国を除く日本全国に佐久鯉が進出するようになる。
「佐久鯉」という言葉はいつから?・・・
大正末期に東京での販売に際し宣伝文句として「千曲の清水と砂利の中で育ち、上州の鯉よりうまい佐久鯉」とうたっているのがはじめて。 |
|
|



![]()
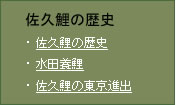
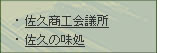


![]()