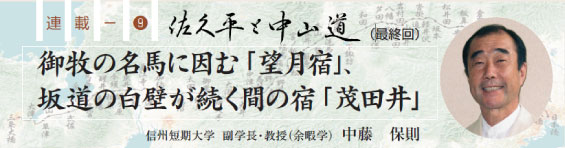 |
|
 |
| 国の重要文化財に指定されている、望月宿最古の旅籠・大和屋真山家 |
北佐久郡、佐久市を通る中山道最後の望月宿は、これまで述べてきた8つの宿駅のなかでは、かなり保存状態がよいといえるだろう。本陣大森家は医院に変わったが、敷地の大半は歴史民族資料館として公開されており、脇本陣兼問屋の鷹野屋は出梁が良好な状態で遺されている。望月宿最古の旅籠・大和屋真山家は、江戸中期明和年間(1764
〜 72)の建物で、国の重要文化財に指定されている。現在も旅館として営業している旅籠・井出野屋は、3 階建ての木造建築である。暴れ御輿と火祭りで知られる榊祭りは、御牧七郷の総社・大伴神社の祭りで、筆者も昨夏、初めて観ることができた。
望月宿は本陣1、脇本陣1、旅籠9 とそれほど大きな宿場ではなかった。望月を有名にしたのは、何といっても名馬である。この辺り一帯は古くから“御牧ヶ原”と呼ばれていたが、文字が示す通り朝廷の官牧が置かれていた。朝廷では旧暦8月15
日に官牧から貢進した馬を天皇が宮廷でご覧になって、御料馬を定める「駒牽きの儀」が行われていた。
なかでも数が多く、名馬を産出したのがこの地域であった。8 月15 日は中秋の名月であり、満月を望月ということから、名馬も望月と呼ばれるようになった。そして、この地域も望月という名で呼ばれ
るようになったという。
宮廷では鎌倉時代まで、大津から京都に入る逢坂の関まで貢馬を出迎える習慣があり、三十六歌仙の一人、紀貫之が『拾遺和歌集』に歌を残している。
「逢坂の関の清水に影見えて今や引くらん望月の駒」 望月宿の次は26次芦田宿であるが、その間に茂田井がある。ここは正式な宿場ではなく、近隣の宿場が混雑して収容しきれない時に臨時に宿場の役目を果たした。そのため特に間(あい)の宿と呼ばれることもあった。相当に大きな集落であり、豪農「武重本家」の白壁をはじめ緩くカーブして続く坂道の両側に、白壁や土蔵が続いている。まさに絵になる風景であり、いつも写生している人や写真を撮っている人を見かける。筆者自身、この坂道を歩くのが好きである。
望月もそうだが、茂田井は江戸時代から酒処として知られていた。武重本家が酒造りを始めたのは、慶応元年(1865)と比較的遅いが、古くから酒造りを手がけ、庄屋もつとめた豪農「大沢酒造」の建物は元禄(1688
〜 1704)初期のものといわれる。その先の白壁の大きな建物も大沢家のもので、民俗資料館や美術館が無料で公開されている。
 |
| 緩くカーブして続く坂道の両側に並ぶ白壁や土蔵 |
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
この連載の第一回に、「歴史についての知識がなければ、シルクロードは、ただ埃っぽい、単調な一本の道にすぎない」という文章を引用した。私にとって中山道は、今や魅力に満ちた歴史古道となっていると述べて、最終回の締めくくりとしたい。 |
|
 |
|

