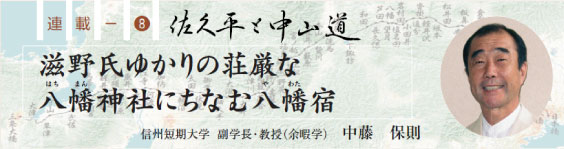 |
|
第23 次塩名田宿と第24 次八幡宿との距離2.91 キロは、中山道で最短、次の望月宿までの3.45 キロも4 番目に短い。その理由は、塩名田宿・八幡宿間が悪路であったため、近隣の集落から人を移住させて造られた新宿であったからである。新宿といっても慶長7
年(1602)というから、江戸幕府が一里塚を造成する2 年前であり、中山道が整備されると共に形を整えていったのだろう。同時に新田の開発も行われ、寛永8
年(1631)から、市川五郎兵衛が私財を投じて拓いた五郎兵衛新田は、そのうちもっとも大規模で名高いものとなった。
 |
国の重要文化財
「高良社」 |
八幡宿の宿場としての規模は、本陣1、脇本陣4,旅籠屋3 と小さいが、脇本陣が4 つもあるのは、休憩や宿泊地として旅人に人気があったことを想像させる。皇女和宮の一行も宿泊に八幡宿を選んだ。
名称の由来は入り口にある八幡神社からきているが、「はちまん」ではなく「やわた」と発音される。八幡神社は高良社、あるいは高麗社とも呼ばれる。古代に高句麗から来た牧馬の技術をもった渡来人が、望月の官牧を指導し、その守護神として創建したものである。その後、牧官から武人として成長した滋野氏は、この神社を八幡社として尊崇した。国の重要文化財に指定されている本殿は、延徳3
年(1491)滋野氏によって八幡社として建立されたものである。奈良時代までは「やはた」とよばれていたという。(注1)八幡宿の八幡神社は古い呼び名が残ったものであろうか。
いずれにせよ八幡神社は、その後も武神として武士や庶民から篤い信仰を集め、何度も修理や寄贈が行われてきた荘厳な神社である。
滋野氏はいうまでもなく、清和天皇の血を伝えるといわれ、平安時代から佐久、小県の両郡に根を張った名門の豪族であったが、やがて海野、禰津、望月の三家にわかれた。知謀の猛将として名高く“真田三代”として知られる幸隆・昌幸・幸村の真田家は、滋野の本家を継ぐ海野氏からわかれた一族である。
 |
八幡宿から望月宿へ抜ける
「瓜生坂」 |
宿場もさることながら、八幡宿を抜けて次の望月宿に至る道にも、なかなか見ものが多い。百沢の双体道祖神は、衣冠束帯と十二単の王朝風祝言像が精巧な浮き彫りになっており、保存状態もよく男女の表情まで見ることができる。この辺りから望月にかけては、双体道祖神が数多く遺されており、腕が良いことで知られた伊那の高遠石工の手になる秀作が見られるという。
元禄10 年(1697)に建立された「中仙道道標」も見逃せないところである。「中仙道」となっているのは、「中山道」に表記が統一された正徳6
年(1716)以前に立てられたからである。
 |
| 八幡宿本陣跡 |
中山道は瓜生坂を越えて佐久平を通る中山道最後の宿、望月宿に入るが、この瓜生坂は古代の東山道にあたり、遺跡も発見されている。 |
|
 |
|

