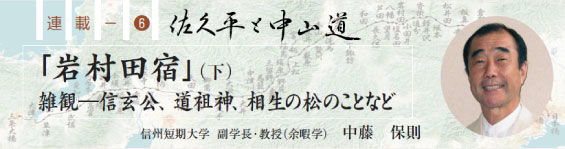 |
|
 |
 |
| 若宮八幡神社と境内にある双体道祖神 |
夏休み、他のゼミ旅行に同行して南信を旅してきた。途中立ち寄った阿智村の長岳寺は、三河の陣中で病没した武田信玄の遺骸を安置したところである。ところが、一説によると、遺言により信玄が帰依していた北高禅師が、遺骨と短刀、袈裟環を佐久まで持ち帰って葬ったという。それが龍雲寺である。昭和6年、同寺の玉垣の支柱が壊れ、修理のために近くを掘ったところ、偶然、骨壺や遺品が発見された。詳しい調査によって、信玄公のものに間違いないと確認されたという。そこで霊廟と五輪塔が造られ祀ってあるが、あまり訪れる人もいないようである。佐久平の人は信玄をそれほど好いていないと聞いたこともあるが、昔、たびたび攻め落とされた恨みが、未だに残っているのだろうか。
中山道を通勤の道に使っているうちに、いつしか道祖神に興味を持つようになった。道祖神は古くから境を守る神であったが、除災、縁結び、夫婦和合、防行疫など様々な信仰が結びついて各地に祀られているものである。なかには男女を浮き彫りにした双体道祖神があるが、これは不思議なことに群馬県と長野県にしか見られないという。
岩村田宿にも双体道祖神があり、住吉神社のものは天明年間に祀られた。若宮八幡神社の境内にある双体道祖神はさらに古く享保19 年の銘があり、男女が神に捧げる由布を持つ珍しいスタイルである。そしてたった一体、宿内の中山道に面している双体道祖神がある。西宮神社の鳥居の下にひっそり立っており、通勤の行き帰りに心の中で手を合わせると、何となく優しい気持ちになれるのだ。
岩村田宿をでてさらに中山道を進むと、浅間総合病院の先で道は左にカーブする。正面に見えるのが相生の松である。江戸に降嫁する皇女和宮が、野点を楽しんだという由緒ある松である。残念ながら初代の松は枯れて、碑が建立されている。相生は相老と同義であり、相生の松はひとつの根本から雄松(黒松)と雌松(赤松)が分かれて生えているもので、仲の良い夫婦に例えられる。和宮の一行にとって縁起が良い場所であった。
追分宿から小田井宿を通り中山道を辿ってくると、岩村田宿はかつての宿場の面影を最も遺していない宿である。宿駅としてよりも交通の要衝、米穀の集積地として栄えた街の性格が影響しているのだろうか。また、新参者の私も地域の方に知り合いが多くなってきたが、常日頃、中山道や岩村田宿はあまり強く意識にのぼっていないようにも思える。
 |
| 「相生の松」の碑 |
私は北海道生まれである。歴史遺産がまったく乏しい地に育った身には、実にもったいなく感じられてならない。そして、余暇学を学ぶ身には、観光・レジャーの大資源が点のように存在しており、活かしきれていないのではないかと思える。そう疑いつつ、岩村田住吉町に住んで喜んでいる毎日である。 |
|
 |
|

