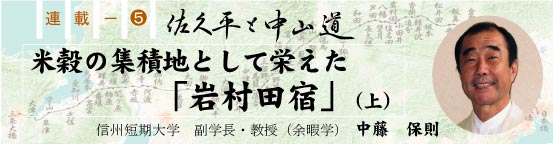 |
|
長野県の地図を見ると、中央部が東に、つまり江戸の方角に出っ張っている。そこが他ならぬ佐久平であり、その中心が岩村田宿である。江戸から数えて22番目、規模も大きく、内藤氏1万5000石の城下町でもあったために大いに賑わった。宿場町の長さは1035.5m、信濃26宿のなかで最も規模が大きかったが、意外なことに宿場としての機能の面ではむしろ小さく、本陣も脇本陣も存在せず、旅籠屋も8軒しかなかった。そのため龍雲寺と西念寺が、本陣、脇本陣それぞれの役を担っていた。岩村田が栄えたのは、宿場としてではなく、信州の入り口であり、穀倉地帯佐久平の中心に位置しているために、交通の要衝、そして米穀の集積地だったからである。
江戸期に入って街道が整備される前、岩村田宿は円満寺の南、荒宿にあった。現在の商店街にあたるいわば「新岩村田宿」が発展するにつれ、荒宿はその役割を譲っていったのだろうが、正徳3年(1713)の「信州佐久郡岩村田宿絵図」には荒宿の通りも描かれている。したがって、少なくとも江戸中期までは、荒宿も岩村田宿として扱われていたと思える。
岩村田宿は相生町の交差点で西に向きを変える。佐久甲州街道の分去れを過ぎて、すぐに京方の枡形にでるが、民家の塀の前に三つの道祖神が立っており、道が小さくカーブしているので、それと知れる。相生町で東の方角を辿れば、日本五大稲荷の一つといわれる鼻面稲荷神社の前にでる。
ところで、私は一人悦に入っている。岩村田宿に住んでいるのだ。住吉神社あたりから宿場が始まるが、その南に善光寺道への分去れがあり、そこを少し下ったところ、龍雲寺の前の少し奥まったところに我が借家がある。短大への通勤はほとんど毎日、岩村田宿を歩き、時々ささやかな“発見”をして喜んでいる。
だが、喜んでばかりはいられない発見もある。先日、短大から中山道にでて、その日は珍しく国道141号バイパスを北に向かった。そこで道路標識を見て異な感じに襲われ、一瞬訳がわからなくなったのである。標識には「← 中山道 塩名田宿 八幡宿 望月宿」とある。私は確か中山道を通り、それを後にして来たはずである。道の反対側にも同様な標識があった。
 |
|
 |
| 本陣、脇本陣の役を担った龍雲寺(左)と西念時(右) |
しばらく考え、自分なりに得た結論は、「← 中山道の塩名田宿・・・」というものであった。それならば正しい。たしかに44号線は、二股に別れ左に進めば塩名田宿にでるからだ。だが、そこへ至るまでの道は中山道ではない。車両向けの標識としてはこれでいいのかも知れないが、中山道を歩きたい人に対しては、誤解を与えるし、不親切な道標ではないだろうか。
|
|
 |
|

