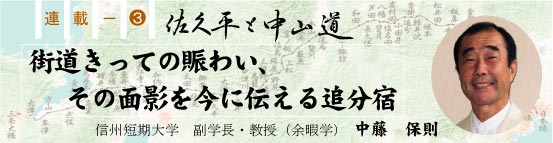 |
|
追分けといい、分去れという。この言葉にはどこかロマンをかきたてる響きがある。中山道20番目の追分宿は、信州佐久平に入った中山道で、往時の面影をもっとも留めている最初の宿駅である。その西の枡形を抜けたところに遺る分去れ(分岐点)で、中山道は北国街道(善光寺道)と分かれ、再び交わることはない。その分去れがあったために追分と呼ばれるようになったという。枡形とは宿場の防衛のために見通しがきかないように入り口を石垣などの土手で囲い、道を鍵の手状に曲げて敵の直進を阻む目的で造られた。
 |
| 平日でも観光客が足を運ぶ |
追分を愛した文学者は少なくないが、その筆頭は「少女趣味の軽井沢作家」と形容された堀辰雄である。彼は追分宿の脇本陣であった油屋の敷地内の家に昭和19年9月から26年7月まで住み続け、家を新築して28年5月に亡くなるまで住んでいた。この家は現在、堀辰雄文学記念館となっている。ただ、「少女趣味」というのは、彼の作品をごく表面的にしかとらえていない形容であると思える。油屋は昭和13年に北側に建て替えられ、旅館として今も営業を続けている。
追分宿は中山道きっての賑わいだった。「追分節」の一節に「浅間山から追分見れば、飯盛り女郎がうようよと」と唄われている。ところがいつの時代にも堅物がいるもので、うようよいる飯盛り女を避けて「平旅籠」と呼ばれた“普通の”旅籠を選ぶ人もいた。
 |
| 追分脇本陣の「油屋」 |
追分は「追分節」発祥の地である。飯盛り女たちが唄った「馬方節」がやがて「馬方三下がり」「追分節」として全国各地に広がり、江戸では流行歌ともなったという。あの独特の哀切なメロディーは日本人の心情に訴えるものがあるのだろう。江差追分、越後追分、本荘追分などが知られている。
いわば本家の「信濃追分」には、こんな一節もある。「追分の枡形の茶屋でほろりと泣いたが忘らりょか」一夜を共にした飯盛り女が、堅物ではないほうの旅人を枡形まで送ってきて別れを惜しんだのだろうか。枡形の茶屋は「つがる屋」の屋号で、現在も遺されている。
追分節は「追分宿郷土館」で聴くことができる。この宿を散策していて楽しいのは、建造物が多く遺されていることに加えて、同館などで見聞きし、入手できる資料や案内書が豊富なことである。また、岸本豊氏が個人で開設した「中山道69次資料館」は、中山道の全体像を知る上で恰好の資料館となっており、筆者もよく訪れてレクチャーを受けている。
 |
| 今でも面影が残る追分宿 |
追分宿は、地域の貴重な文化遺産であり観光資源であるが、老朽化が進んでいる建物もあると聞く。ぜひ保存・保護の手を緩めず、訪れる人を長く楽しませてもらいたいと願っている。
|
|
 |
|

